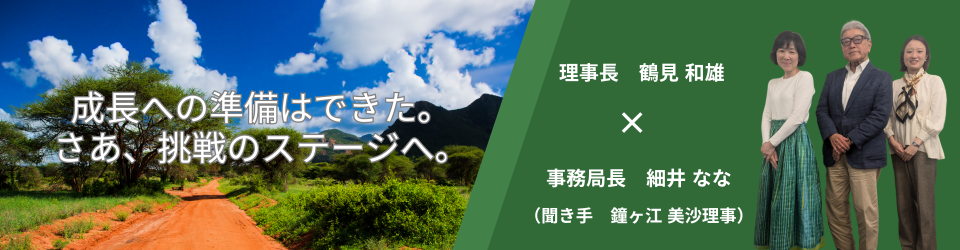
ー2024年はどのような年だったでしょうか。
細井 活動を今一歩前に進めるための、「脱皮」の年になりました。過去10年間、厳しい環境の中で適正化施策とガバナンス強化に取り組んだ結果、組織にしっかりとした土台ができ、「次の段階」への準備が整ったと感じています。
鶴見 過去には寄付を大切に使おうとするあまり活動が慎重になる傾向もありました。しかし、ガバナンスの強さがハンガー・フリー・ワールド(HFW)の長所と自信が持てた2024年ごろから組織全体に、新しいことに挑戦し成長しようという機運が高まってきたと思います。さまざまな適正化施策を乗り越え、十分な力を蓄えて前進に転じるという経験は、今後の大きな糧になるでしょう。

理事長 鶴見 和雄
三菱商事、プラン・インターナショナル・ジャパン専務理事などを経て現職
事務局長 細井 なな
政府系国際協力機関や子ども支援NGOに勤務後、2020年にHFW入職。海外事業部門マネージャーを経て現職
理事 鐘ヶ江 美沙
2025年に就任。HFWでボランティアを経験し、現在はあずさ監査法人に勤務
※ 役職名は取材当時のものです
ー海外事業については、どのように振り返りますか。
細井 2024年は3ヵ国の事業地の住民に、活動を住民組織に移行し支援を終える計画を明確に伝えた年でした。活動地にとっても、「支援が終わる時」に向かって自分たちで準備を始めるという意味で「転換点」だったと思います。
支援が長くなりすぎると、住民の決める権利と真の自由を奪いかねません。また私たちも飢餓のない世界という目標に向かうためには、いつまでも同じ地域に留まるわけにはいかない。ただ住民が安心して「卒業」の日を迎えられるよう、彼ら彼女らに納得してもらえるまで支援終了の理由を説明し、自立への計画づくりもサポートしていきます。
鶴見 HFWの存在意義は、単にモノやノウハウを提供するのではなく、住民が自分の力で、経済的な自立と幸福をつかめるようサポートをすることです。それによってSDGs目標2「飢餓をゼロに」 だけでなく、「貧困をなくそう」など他の目標にも包括的にアプローチできるのです。また2024年11月に訪れたバングラデシュでは、女性グループ連合会のメンバーがミミズ堆肥を生産し、これを販売することで大きく家計を支えていました。現在は、その生産技術を他の農家にも伝授し、地域全体でどんどん広がっています。それを見て、他地域に向けても成功事例を横展開する必要性を強く感じました。飢餓をなくすことを考えれば、 大切なリソースをいかにより多くの地域に横展開させていくかも、HFWの大きな挑戦となります。

細井 事務局を務める「世界食料デー」月間や、書損じハガキ回収キャンペーンへの参加団体・企業がこの数年で急速に増え、地道な活動が実を結び始めています。私たちの活動が多くの人に支えられていることも実感できました。
法人担当を増員して、財源確保についても新たな挑戦を始めています。ただ受益者の利益が最優先であり、資金を得るために本来の事業を歪めてはならないことも、肝に銘じています。
鶴見 食料自給率38%(※カロリーベース)の日本において、食の安全保障は重要なテーマです。HFWは活動地の現状を日本へ伝え、さらに多くの企業・団体や個人と日本も含めた世界全体の食の問題を考えることで、社会に変化を起こせる可能性を持っています。これからはアドボカシーにも大いに期待していきたいですね。
ー 今後の抱負をお聞かせください。
細井 まずは2024年からの中期計画を、スピーディーに進めていきたいです。ただ「if you want to go fast, go alone, if you want to go far, go together(早く行きたければ、一人で進め。遠くまで行きたければ、みんなで進め)」 のことわざもあるように、飢餓なくすという大きな目標に向かうには、時間をかけて受益者や支援者のみなさんと対話することも大切だと思っています。理事会のみなさんには、事務局が慎重になりすぎた時、ハッパを掛けてもらいたいです(笑)。
鶴見 組織の風通しの良さとお互いを尊重し合う風土、そして活動のたびに振り返りを行い次に生かす姿勢は、HFWの大きな強みです。こうした良さを守りながら、恐れることなく挑戦に向かっていきたい。それによって次の5年が、HFWにとって「達成」の時期になればと願っています。
(2025年4月収録)





