
みなとみらい駅にて。向かって左から理事の西岡、事務局長の細井、理事長の鶴見、副理事長の籠島
2025年8月20日から22日の3日間にわたって行われた、第9回アフリカ開発会議(Tokyo International Conference on African Development:略称 TICAD)。
アフリカの開発をテーマとする国際会議で、日本政府の主導のもと、国連や国連開発計画(UNDP)、世界銀行、アフリカ連合委員会(AUC)と共同で開催され、アフリカ各国の要人や関係者が参加。3年に1回、日本もしくはアフリカで開催されます。
TICADはアフリカ諸国のみならず、開発に携わる市民社会、国際機関、民間企業が参加。アフリカのオーナーシップの尊重と、国際的なパートナーシップの推進を基本理念に掲げています。
ベナン、ブルキナファソ、ウガンダの3カ国に事務所を置く、ハンガー・フリー・ワールド(HFW)。スタッフ数名も現地訪問やオンラインのセミナーを聴講するなど、情報収集を行いました。今回はその中から事務局長の細井、ブルキナファソ・ベナン担当の内野へ、インタビュー形式でそのご報告をさせていただきます。聞き手は広報担当が行いました。
ー TICADは横浜のみなとみらいで行われましたね。会場の様子はどうでしたか?
(細井)みなとみらい駅を降りてからTICADの看板や旗が掲示されていて、TICAD一色といった様子でした。会場のパシフィコ横浜までの道も、行き交う人がアフリカから来ている様子の方でにぎわっていました。
はじめにビジネスEXPO(企業を含むアフリカ開発に関わる)のJETROブースへ訪問しましたが、そちらもにぎわっていて過去最大の訪問者数だったそうです。
各ブースで商談が活発に行われ、関心が年を追うごとに高まっていることを感じました。日本側もコンサルタントやスタートアップをしている若い人が多数参加しており、これから新しいことがどんどん起こっていきそうな期待を感じました。
(内野)ITなど新しい分野なので、アフリカ側も若いアクターが多かったですね。
変化するアフリカ
ー 「アフリカ」というこれまでのイメージとは違った、新しい側面が見えてきたのですね。
(細井)書損じハガキなどでご協力いただいている銀行なども出展され、ステージでファイナンスをテーマにした講演もあり、金融も大事だなと思いました。
(内野)私がJICA海外協力隊の隊員で行っていた1990年代から比べると、今はATMが増えて、地方に銀行があり、普通の人が現金を引き出せることに驚きました。金融がアフリカの市民社会に入り込み、多様になっています。
最近では携帯電話会社経由で海外からの送金もでき、お金のやり取りを自由にできることはビジネス参入ができるという点でも大きいですね。
ー 携帯電話の普及やインターネットを介した送金システムなどの話を聞くと、遠いアフリカとはいえ、わたしたちと同じ時代を生きている人たちなのだなと感じますね!
HFWとアフリカの関わり
ー 今回TICADへは、どのような目的で訪問したのでしょうか?
(細井)アフリカ3ヵ国で活動する団体として、現状の環境にはアンテナを張っておきたいからです。TICADはアフリカ全体を捉えられる貴重な機会。今は地球規模でさまざまな問題が関連し合って起きているので、全体の動向をつかむことは重要です。
ー 実際に行ってみて、いかがでしたか?
(細井)さまざまなアクターが動き、環境が変わっていると感じます。
活動地の村々は時間の流れがゆっくりですが、彼ら・彼女たちが生きている大陸のアフリカでは、多様な取り組みがなされていることを俯瞰して見ることができました。
たとえば、これまでは農業トラクターといえば大型のものが多かったのですが、今は小回りのきく、悪路でも動きやすい現地の状況に合ったものが開発されていることなどが紹介されていました。
私たちも活用できるところや、つながれるところを検討するにあたって、視野を広げる機会となりました。
ー そうした最新鋭の技術と、農村で行われているHFWの活動は遠いようにも感じられますが、どうつなげてゆくのでしょうか?
(細井)そうですね、そこで議論されていたのは技術は外から持って来るものではなく、中からの技術を活かすもの。本当にそこで必要なもの、適しているもの、合っているものはその地域の人たちが一番わかっているということですね。
それを地域住民の目線に立ってアプローチすることは、HFWが現場のことをよく知っている団体であるので、その知見を活かす役割を担ってゆけると考えています。
もっと言えば、HFWがエンパワーメントの取り組みを進めていった先に、地域住民が多様なアクターと自ら連携したり取り組みを進めたりしていけるような魅力あるコミュニティになっていって欲しいですね。
日本とアフリカ、私たちにできること
ー TICADの中でも、NGOとして何ができるかといった視点の「市民社会を通じた開発を再構築する」というテーマ別イベントに参加されたおふたり。
日本社会ではまだまだアフリカは遠く感じられますが、いち市民として何ができるのでしょうか?
(内野)アフリカでは、自分からその話題を出していないのに、「原爆を落とされているのに、あそこからどうやって復興できたの?」と現地の学生が日本について知っていて聞かれることも少なくありません。アフリカの人に、日本が知られていて、関心を持たれていることを日本の人があまり知らないことが残念です。
今はアニメから知って、もっと身近に感じている人も多いのですよ。
(細井)日本への期待値は高いですよね。
一方で、女性や若者の活躍の機会が限られているといったような、共通の課題も抱えています。彼女ら・彼らの参加できるプログラム開発や、視点を活かしたイノベーションについても議論されていました。市民社会では、こうした課題を共有し、さまざまなアクターの良さを活かして、学び合いながら解決へ向けてゆくことができるのではないでしょうか。
ー アフリカといえば、不安定な情勢など一部分にフォーカスされがちですが、前向きな議論が行われていたのですね。
(細井)暴力、過激派の脅威はありますが、現状認識し立ち向かってゆこうといった発表もありました。
特に印象に残ったのは、コアラガさん(ブルキナファソの国際関係戦略研究所 事務局長)の「暴力は格差から生まれて来るものだから、防げる。平和で包摂的な社会開発が大切で、どこに住んでいてもそれは同じで大切。」という言葉です。
どうしても貧しい生活に困って、満足な職も得られないような状況の人たちは、反社会的な勢力に取り込まれやすい。だからこそ、格差をなくすことが大事で、それはアフリカでも日本でもお互いに影響するし、関係することだと思います。
TICADから見えた、HFWの役割と「誰も取り残さない」活動
(内野)現地の担当者として印象に残ったのは、「地域の人たちから発言させて欲しい」という議論でした。
私たちのように介入する側は調査で聞き出すことはしますが、現地の人がそれに関してどうだったのかと議論する場がまだまだ少ないと反省しました。
(細井)私たちの自立への取り組みには5つのフェーズがあり、その中で現地の住民が自らモニタリングしてその結果を活かし、また計画を立ててゆくということを目指してやっている最中ですね。2016年から2020年の中期計画ではまさにその点について反省があり、次回はより良くしていこうと現在取り組んでいますね。
(内野)そうですね。
気をつけなければいけないのは、たとえば現地で女性が会議中に発言しないことはジェンダーギャップじゃないか、と介入する側は言いたくなる。でもその地域では伝統的に女性が発言することがないから、それが恐ろしい、怖いという人もまだまだいる。だからこそ、それが何に起因するのか知っておかないと、逆の効果を生んでしまうことがあります。
(細井)そうですね。やり方によっては、そういったもともとの力関係や格差を、私たちが固定化しかねない場合もありますね。
(内野)そうした変化を生んでいくことは、やろうと思ったら時間がかかります。ただ今の世の中はとにかく早いものを求められるので、そういった長期的な視点はおざなりにされがちです。
しかしこうした女性が発言できない問題はずっと残ってしまうし、早く進めないアプローチが大事だということを言っていかないと、隅に追いやられる人はさらに置き去りにされるのではないかと思いました。
「誰も取り残さない」ということは大切で、そのスピードから取り残されている人はたくさんいるからです。腰をどっしり据えた、長期的な視野に立って活動を行っている団体は日本で少ないですよね。
TICADは開催した後が大事で、今回話し合われたことが、これからどう展開してゆくのか注視していきたいです。
ー 今は世界的に排外主義が強まり、異なる人同士が連帯していこうという声がかき消されそうになることに、個人的に危機感を抱いています。
(細井)場所は違うけれど、良いものを食べさせ、良い教育を受けさせ、良い地域を創っていきたいと思う人の気持ちに変わりはありません。
日本でも自然災害が起きると取り残される人がいて、災害が起こったときに助け合うことが学びとして蓄積されています。それが地域レベルなのか、地球レベルなのか、という違いではないでしょうか。
特に気候変動は地球レベルで起こっていて、対策も途方もないものと思いがちですが、地域地域、一人ひとりの取り組みに効果があります。
(内野)かつてTICAD市民社会フォーラム(※)のメンバーと、「TICADは必要なのか?」というテーマで議論したことがありますが、「数年に一回でも、アフリカを報道でメインで出してもらえる。滅多にアフリカの報道がない日本においては、その意義がある。」という発言にみんな納得しました。
今や世界はつながっているという感覚を持つことが大切で、日本は日本だけでは生きてゆけないことを市民社会レベルだけでなく、政府も大きく発信してゆく必要があると感じています。
(細井)気候変動や世界平和、そしてフードシステムも、世界はどこかでつながっています。
どこかでがんばっている人を見ることも、お互いに励まされます。農家の人たちが一生懸命に力強く、自分たちの工夫や経験をプレゼンしている姿を見ることで、こちらも元気が出てきます。
ー そうですね!同じ人間として尊敬する気持ちがあれば、分断を乗り越えて連帯してゆく未来が創れそうですね。今日はありがとうございました。
※TICAD市民社会フォーラム:2008年の第4回TICADをターゲットに活動していた期間限定のシンクタンク型NGO。内野が理事を、西岡が事務局長を務めていた。

テーマ別イベントの様子
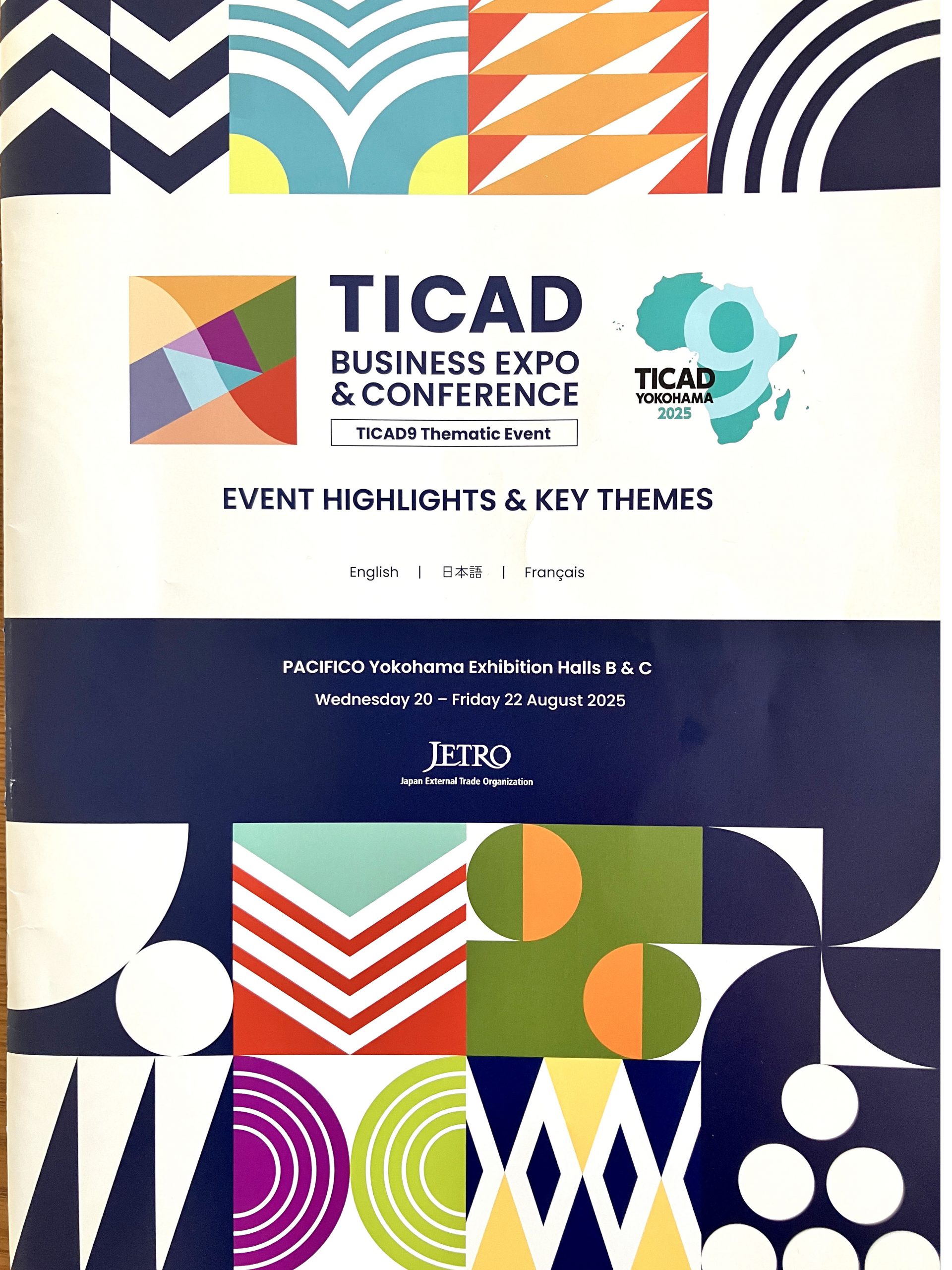
TICAD 9のパンフレット
