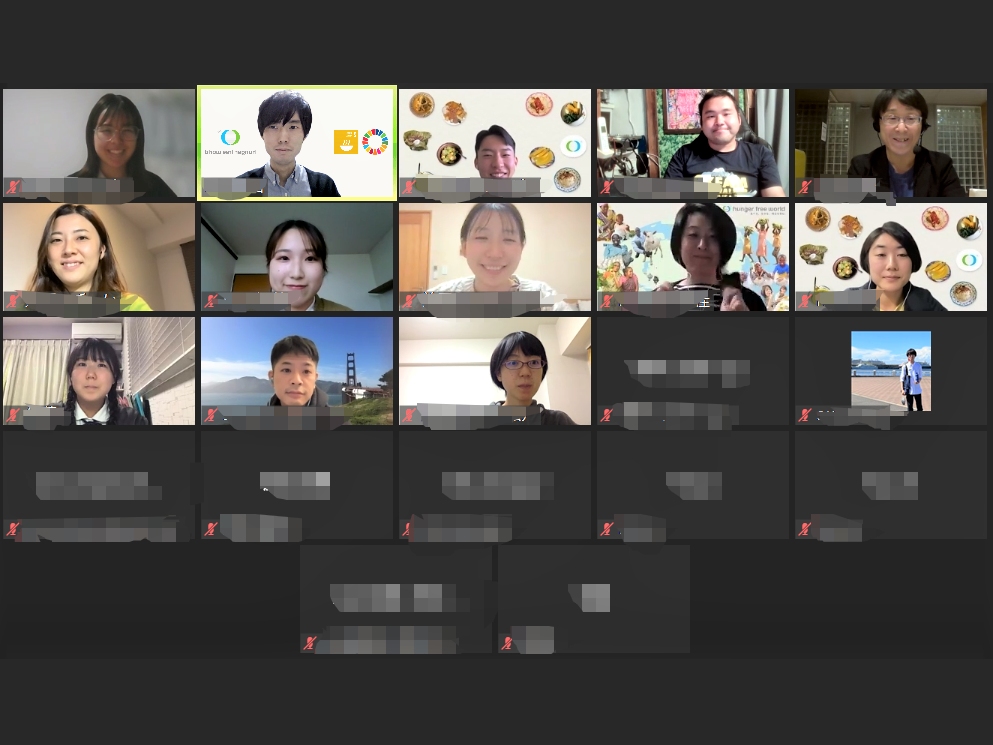
2022年10月の中間発表会はメンバーの理解を整理し、参加者からアドバイスをもらう機会になりました
日本の食のしくみを変えることで世界の飢餓の解決を図る「フードシステム変革推進チーム」の1年目が終了しました。日本で行うアクションを計画するため、初年度は「日本の食が世界の飢餓にどう影響しているか」を調査。2023年3月、国連食糧農業機関(FAO)駐日連絡事務所の日比絵里子所長から講評を受け、1年目の活動を締めくくりました。
メンバーは、温室効果ガスの8~10%がフードロスによって排出されている1ことから、日本のフードロスの削減が気候変動を抑制し、飢餓の解決に寄与するなど、いくつかの結論を発表しました。日比所長は、気候変動などは地球規模の複合的な問題のため、日本一国の取り組みが与える影響を示すことは難しいと指摘する一方、事実や既存の取り組みを整理することはとても重要であると講評。学ぶことこそが解決に向けた第一歩になると、チームへの高い評価と大きな期待が寄せられました。メンバーも「活動に参加して食生活が大きく変わった」と前向きに話しています。
複雑な問題でも1つずつ主体的に学ぶことが行動変容につながると、メンバー自身が実証した1年。今後は2期生が学びを続けながら、行動へとつなげていきます。
※1:Mbow et al.(2019)

最後の月例ミーティング。「1人のアクターとしてできることを続けたい!」と決意を語りました。

気候変動や開発途上国の貧困は、地球規模の複合的な問題です。そのため、日本でとる一つの行動が、最終的に世界レベルでの大きな課題にどのように影響を与えるのかを量ることは至難の業です。ましてや、その効果を数値化することは難しいです。一方で、地産地消であれば「地元の産品の保護」など、さまざまな取り組みがあり、それぞれに異なった効果があります。グローバルな飢餓の解決を理由に特定の取り組みを推進するより、まずは既存の取り組みやその背景にある事実を整理してそれぞれが貢献する内容や効果などを明らかにすれば、食をめぐる複雑な環境を理解するための第一歩となるのではないでしょうか。
FAO駐日連絡事務所 日比絵里子所長
同じ志を持ちながらも、違う知識や視点を持つメンバーや職員の方々と活動する中で、学びの多い一年になりました。フードシステムの複雑さに圧倒されることもありましたが、活動を終えてみると変化は起こせるという前向きな気持ちが残っている気がします。今後も一人のアクターとしてできることを続けていきたいです。
フードシステム変革推進チーム 小山さん
大学一年生で挑戦して、自分の力不足もたくさん感じましたが、力不足のせいにせず、取り組めたことは自信になりました。もっと力をつけて形にすること、また、ひたむきさを忘れずにこれからも自身がアクターとして活動していきたいです。こう思えたのも職員さんを含めたチームの皆さんのおかげです。ありがとうございました!
フードシステム変革推進チーム 水野さん
「飢餓をなくす」ことへのジブンゴト化が大きく前進した実感があります。課題は想像以上に複雑で困難であることを痛感しながらも、同じ方向を向くメンバーと、真剣にこの課題に立ち向かったプロセスがとても豊かな時間でした。微力でも無力ではないと信じて、自分にできることを継続していきます!貴重な機会に感謝です!
フードシステム変革推進チーム 林さん
